「心電図異常」とは?
- 2025年5月16日
- 健康診断・人間ドック,検査,その他
「心電図異常」と指摘されたら―それは見逃せない“体や心臓からのメッセージ”
健康診断の結果通知。そこに「心電図に異常を認めます」「精密検査をおすすめします」と書かれていたら、不安になるのは当然です。
しかし、心電図異常はすべてが「病気」「治療が必要な状態」とは限りません。大切なのは「何がどう異常なのか」を正しく理解し、適切な対応をとることです。
心電図が映し出すものとは? 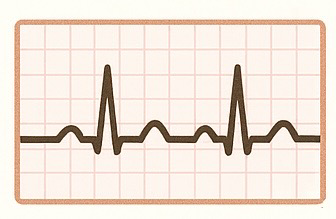
心電図は心臓の電気的活動を記録した波形です。心臓は、洞結節という部位からの電気刺激によって規則的に収縮と拡張を繰り返しています。
この電気信号が心臓の各部位に伝わる過程やタイミングを読み取ることで、不整脈、心筋虚血、伝導障害など、さまざまな病的状態を推測することができます。
心電図の異常とされる所見には以下のようなものがあります:
- 洞性徐脈・洞性頻脈
安静時の脈拍が極端に遅い(徐脈)または速い(頻脈)状態。スポーツ選手などでは生理的な徐脈も見られますが、極端な場合は洞不全症候群などの不整脈の疑いがあります。 - 期外収縮(上室性・心室性)
規則的な拍動の中に突発的な「余計な拍」が入る現象。単発であれば心配ないことが多いですが、多発・連発する場合や症状を伴う場合は精査が必要です。 - 脚ブロック(右脚ブロック・左脚ブロック)
心室へ電気信号が伝わる際の伝導障害。右脚ブロックは比較的よく見られ、必ずしも病的とは限りませんが、左脚ブロックは心疾患(特に心筋症や虚血性心疾患)と関連していることが多く、注意が必要です。 - ST-T変化(ST低下・T波陰転など)
心筋の酸素供給が不足している可能性を示す波形変化。虚血性心疾患(狭心症や心筋梗塞)の兆候として見られることがあり、胸痛などの症状があれば緊急性を伴う場合もあります。また、慢性に指摘されているものでも心筋症が見つかる場合もあります。
精密検査は「確認のステップ」
心電図の一回の記録だけでは、実際のリスクを判断できないこともあります。たとえば一過性の不整脈や、精神的緊張による変化など再検査では正常となることもあります。
必要に応じて行われる検査には次のようなものがあります(当院でも行っております)
- 24時間ホルター心電図:長時間の記録で、日中の活動時や就寝中の心拍の変化をチェックします。
- 心エコー(超音波検査):超音波を使って心臓の大きさや形、心臓の動き(ポンプ機能)、弁の状態をチェックします。体への負担も少ない検査です。心臓の大きさや心臓の筋肉の厚さ、心臓の動きや弁膜症の有無を確認することが可能です。
- 血液検査(心筋トロポニン、BNPなど):心筋のダメージの有無や、心臓への負担がないかをチェックします。

放置せず、正しい診断と管理を
自覚症状がないからといって、放置するのは禁物!中には、心筋梗塞や不整脈、心房細動などの前兆を示している場合もあります。一方で、問題ないと判断された場合でも、年齢や既往歴、生活習慣によっては定期的な経過観察が推奨されることもあります。
当院の検査体制 
医師が診療をしながら超音波検査をしてもどうしても詳細な評価は難しいと考えています。当院では大病院と同様、超音波検査のプロである臨床検査技師による検査体制を設け、30分以上をかけて詳細な評価を行っております。また、血液検査も当日検査結果が出ますので、心電図の異常に関する不安を原則当日に解決できることができます(例外的に混雑状況により、どうしても当日のご案内が難しい場合があります)
最後に:心電図異常は「未来へのヒント」
健診での心電図異常は、体や心臓からの「何か違うよ」というサインかもしれません。
「早期発見できたこと」を前向きに捉え、専門医の診察を受け必要に応じた検査を行うことが大切です。
特に高血圧、糖尿病、高コレステロールなどの生活習慣病がある方は、心臓への負担が蓄積されている可能性もあるため、放置せず一度専門医に相談しましょう。

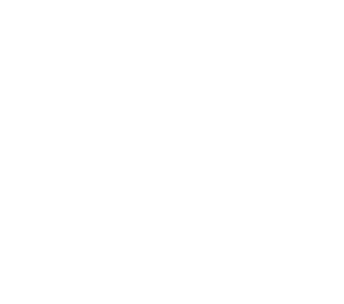 心不全専門サイト
心不全専門サイト

